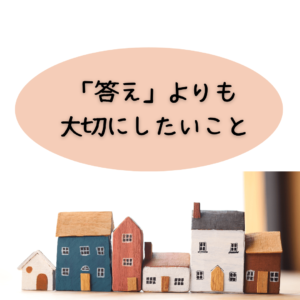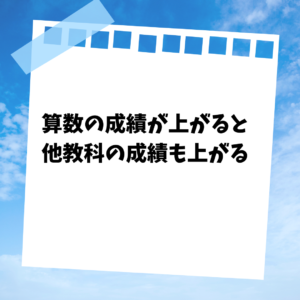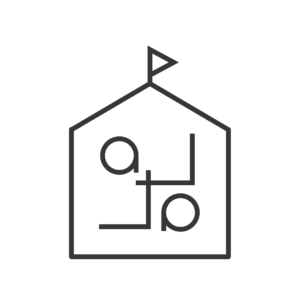「うちの子、遊んでばかりで全然勉強しないんです……」
これは、小中学生を持つ保護者の方からよく聞かれるお悩みのひとつです。特にテスト前や宿題の多い時期になると、つい「遊んでないで勉強しなさい!」と強く言ってしまいがちです。
しかし、その言葉が子どものやる気をそいでしまっているとしたらどうですか?
実は、勉強時間を確保するために「遊びを取り上げる」のは、逆効果になることがあります。今回は、子どもの“遊び”をどう捉え、どう活かすことで勉強習慣を身につけていけるかについてお話しします。
遊びを取り上げると勉強は進まない?
子どもにとって遊びとは、ただの気晴らしではありません。遊びは、脳をリセットしたり、感情を整えたり、想像力を育てたりする大切な時間なのです。実際、心理学や脳科学の分野でも、「遊びがもたらすポジティブな影響」は広く認められています。
しかしながら、保護者の中には「遊び=勉強のさまたげ」と捉えてしまう方がいらっしゃいます。そのため、「遊ぶのをやめさせれば、勉強時間が増えるはず」と思ってしまうのです。
ところが、遊びを取り上げることで子どもはストレスを感じ、「親に管理されている」という不満や反発心を持つようになります。そして、肝心の勉強にも集中できなくなるのです。
勉強と遊びは対立するものではない
そもそも「勉強か、遊びか」の二択で考えてしまうこと自体が、少しもったいない考え方です。勉強と遊びは、本来対立するものではなく、バランスをとって組み合わせることで、相乗効果を生むものです。
大人だって、ずっと仕事だけしていては疲れてしまいますよね?適度な休憩や趣味の時間があるからこそ、仕事に集中できるようになる。それと同じで、子どもも遊びの時間を挟むことで、勉強に向かう心の余裕が生まれるのです。
実際に効果があったスケジュール例
あるご家庭のケースをご紹介します。
小学校高学年のお子さんがいるその家庭では、毎日遊ぶ時間が長く、親は「もっと勉強させなきゃ」と悩んでいました。そこで、無理に遊びを減らすのではなく、次のようなルールを取り入れました。
「遊び30分 → 勉強30分 → 休憩10分」
「宿題を終わらせたら、30分好きなことをしていい」
「夕方5時〜6時は“集中タイム”」として親もスマホを見ない
この結果、子どもは“遊べなくなる”不安がないため、素直に勉強に向かうようになりました。さらに、「約束を守ったら楽しい時間が待っている」という安心感もあり、時間管理の意識まで身についたそうです。
子どもの自律を育てる関わり方
子どもにとって、「やらされる勉強」は苦痛です。逆に、「自分で決めた勉強」は意外とスムーズに進むことがあります。
そのために大事なのが、親子でスケジュールを一緒に決めること。
「今日は何時から勉強する?」 「遊びの後、どんな順番でやろうか?」
こうした問いかけは、子どもの“主体性”を引き出します。
また、遊びを「禁止」するのではなく、「一緒に考える」スタンスを取ることで、子どもは「見守ってくれている」という安心感を持ちます。
親が先回りして制限するより、信じて任せることが、結果として自律心を育てることにつながります。
遊びを活かすことで勉強の質が上がる
もう一度大事なことを整理しましょう。
- 遊びは、脳のリフレッシュや感情の安定に必要な時間
- 無理に取り上げると、勉強に向かう意欲を失わせる
- スケジュールに遊び時間を“組み込む”ことで、勉強も集中しやすくなる
実際に、一定時間ごとに「遊び→勉強→休憩」のサイクルを取り入れると、学習効率が上がるという研究もあります。
つまり、「遊び=勉強のさまたげ」ではなく、「遊び=効率アップの味方」と考えることが、親としての一歩先のサポートになるのです。
まとめ:遊びも勉強も、“味方にする”スケジュールを
子どもの毎日には、「遊びたい!」「でも宿題もある…」という葛藤が常にあります。
そんな時、親が「じゃあ一緒に予定を立ててみようか」と寄り添うだけで、子どもの中にある“やる気のスイッチ”が自然と押されることがあります。
勉強時間を確保するために、まず大切なのは「遊びを禁止する」ことではありません。むしろ、遊びの時間も大切にしながら、勉強とのバランスを取ること。
親子でスケジュールを共有し、「遊び→勉強→休憩」というサイクルを生活に取り入れてみてください。子どもはきっと、自分の力で動き出すはずです。
そして何よりも、親の声かけひとつで、子どもの気持ちは大きく変わります。
「遊んだら、今度はちょっと頑張ってみようか」
そんな一言が、子どもにとって勉強への“前向きな一歩”になるかもしれません。
これからも、子どもたちが「自分で考えて動ける力」を育てていくために、私たち大人ができるサポートを考えていきたいですね。